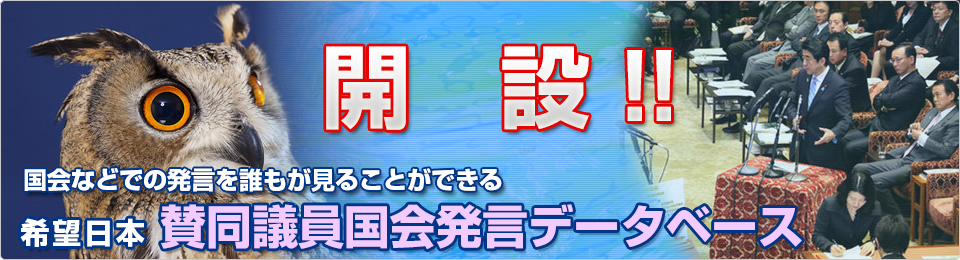合法化される流れのカジノ法についてまとめてみた
カジノを含む統合型リゾート施設(IR=Integrated Resort)整備推進法案(通称・カジノ法案)が2016年12月15日、可決・成立しました。
カジノ法は、カジノをはじめ、会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設など複合的な観光施設を、民間事業者が設置・運営をすることで、観光・地域経済振興などに寄与することを目的としています。
原則、カジノのような賭博を禁じている日本で、同法により合法化の流れができたことになります。

カジノとは?
では、このカジノとは一体、どんなものなのでしょうか?
カジノとは、ルーレットやトランプなどのゲームで金銭を賭ける賭博施設を指します。
ヨーロッパ起源とされますが、1940年代から発展したアメリカ・ラスベガスが著名。
現在、カジノは世界120か国以上で合法化され、世界中に2000軒以上のカジノ施設があり、観光資源の1つとして、集客の世界的競争が行われている、とされるものです。
ちなみに世界のカジノの売上は合計すると1700億米ドル(約18兆円)ともいわれています。
今回成立した法律により日本でもカジノ整備が可能な流れになったのですが、当然この経済効果への期待があるわけです。

日本の賭博・ギャンブルとは
日本ではこれまで刑法上、賭博行為が禁止されているため、カジノは認められませんでした。
では本当に日本に賭博施設はないのでしょうか?
いいえ、だれもが知るように、競馬、競艇、競輪、オートレースなどがあります。
この4事業は、「公営競技」といわれ合法的な賭博として認められています。
公営競技とは、地方自治体が主催することで認められている公営ギャンブル。
根拠となる法律・成立年と、国の監督官庁は
・競馬:競馬法(中央競馬:1954年、地方競馬:1948年)、農林水産省
・競艇:モーターボート競走法(1951年)、国土交通省
・競輪:自転車競技法(1948年)、経済産業省
・オートレース:小型自動車競走法(1950年)、経済産業省
となります。
この4事業のほか「合法的な賭博」には、宝くじと、スポーツ振興くじ(toto)の2つの公営くじがあります。
ここにも法律があり、その成立年と監督官庁は
・宝くじ:当せん金付証票法(1948年)、総務省
・振興くじ:スポーツ振興投票法(1998年)、文部科学省
となっています。
こうした公営ギャンブルは、公共が賭博を差配することで合法化されているのです。
しかし民間主体でありながら、ギャンブル的要素を持つ施設として忘れてならない施設にパチンコがあります。
グレーだともいわれますがパチンコはあくまでも賭博、ギャンブルではない位置づけなのです。

日本の賭博・ギャンブルの市場とは?
こうした公営ギャンブルなどの市場はいったいどのくらいあるのでしょうか?
あるデータによると、公営競技、公営くじ、パチンコの売上高合計は、1995年の時点で約40兆円でした。
ところが厳しい経済情勢などを受け、2013年には24兆円にまで縮小してしまった、といわれています。
2013年時点を基準に内訳を見てみましょう。
中央競馬の2013年の売上はピーク時の6割、2兆4049億円でした。
地方競馬はピーク時の3割、3553億円。
競艇はピーク時の4割、9475億円。
競輪はピーク時の3割、6063億円。
オートレースはピーク時の2割、687億円。
4公営競技はどれも減少傾向です。
公営くじはどうでしょうか。
宝くじは、2013年が9450億円、2001年以降1兆円前後の売上高で推移しています。
スポーツ振興くじは、2013年に、これまで最高の1080億円を売り上げています。
日本のギャンブルの中では比較的良い状況なのですね。
さてパチンコですが、1995年に売上30兆9020億円を計上したのですが、その後減少を続け、2013年にはピーク時の6割、18兆8180億円にまで縮小してしまいました。
40%ダウンという大変厳しい状況なのです。

カジノ法の今後の動き
日本の公営ギャンブルなどが厳しい状況の中で新たに登場したカジノ。
カジノ法は成立しましたが、しかしすぐカジノがつくれるわけではありません。
それどころか、まだカジノは合法化されたわけではない、とされています。
合法化のためには、国が設置区域の選定手続きや、収益の使途などを細かく定めた「実施法案」が必要になります。
国はこの「実施法案」を1年以内に策定することになっています。
またギャンブル依存症対策に必要な措置などをまとめる意向を示している。
要はカジノで指摘されている負の影響への対策を講ずるというわけです。
そのため内閣に、特定複合観光施設区域整備推進本部を置き、検討を始めることとなっています。
今回のカジノ法では、設置区域指定は、「地方公共団体による提案・申請をもとに、国がこれを評価・判断し、指定する」。
そして、「指定を受けた地方公共団体は、自らの費用とリスクによって整備し、運営する民間事業者を公募により選定すること」とあります。
地方自治体が主導的な役割を担うことになっている。
そのため現在、北海道、横浜市、大阪府、長崎県などが誘致に名乗りを上げています。
今後の動きに注目していきたいですね。
※市場データは大和総研レポートから